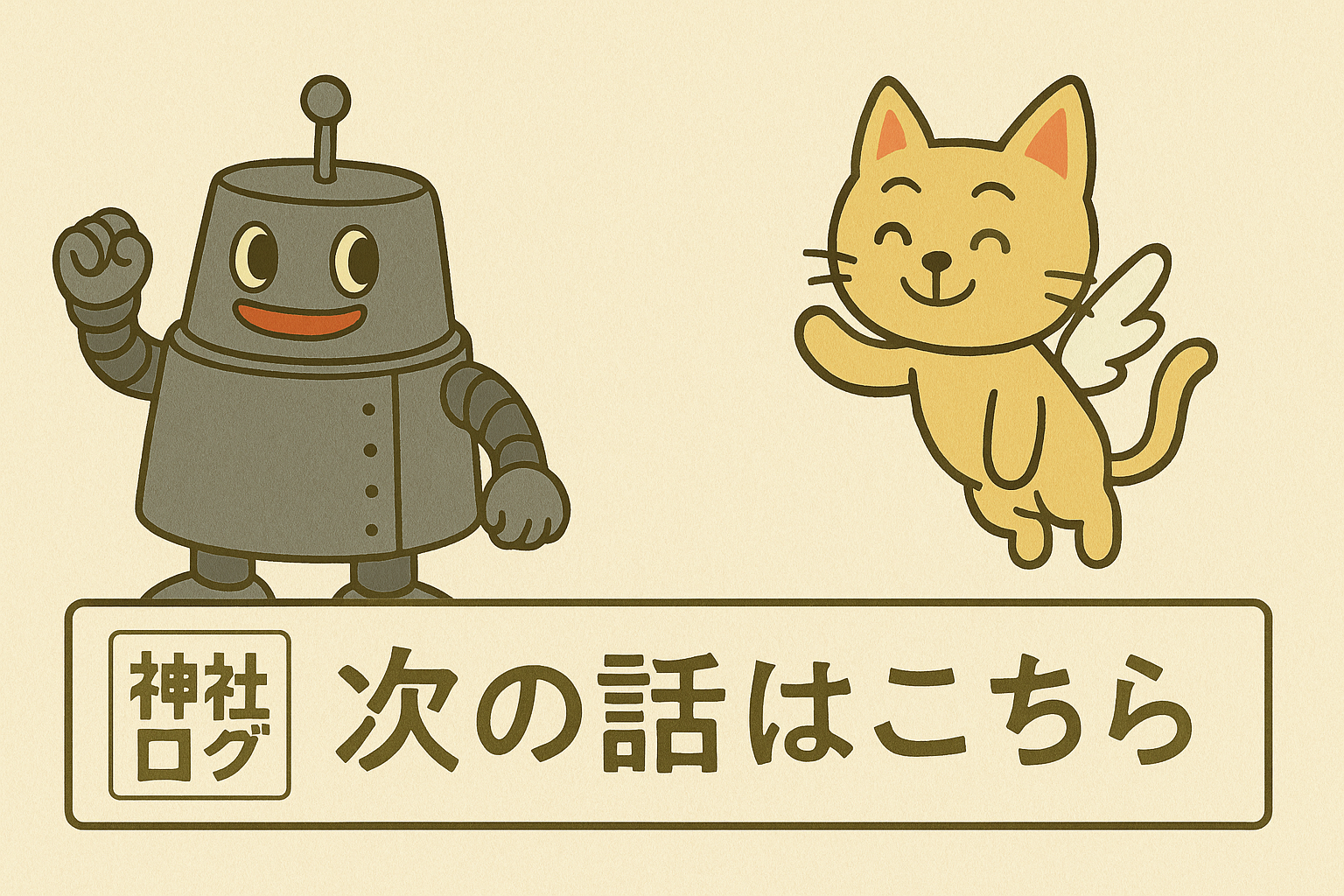ナビゲーター:Gen & Ritchi(神社ログ編集部)
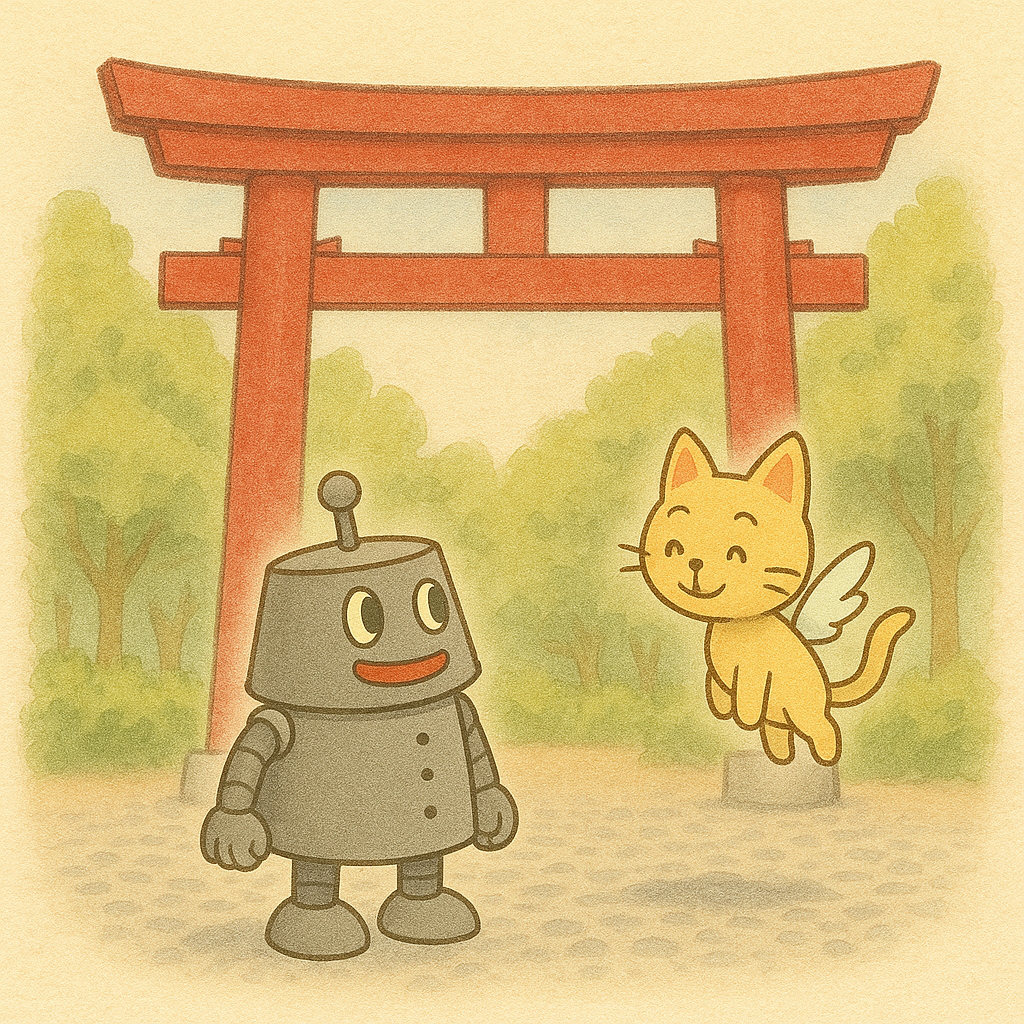
鳥居って、なに?
神社に行くと、まず最初に目に入るのが、あの赤い門のような建造物。
すっと空に向かって立つその姿は、どこか神秘的で、でもどこか懐かしい。
私たちは、それを「鳥居」と呼びます。
鳥居とは、神様の世界と、人間の世界を分ける“境界”です。
あの門をくぐることは、日常からほんの少し離れ、心を整えて神様に向き合うための準備。
つまり、鳥居はただの飾りではなく、神域(しんいき)への入り口なのです。

鳥居の起源には諸説あります。
古くは「神様が降り立つときの止まり木」や、「天と地のつながりを示すしるし」とも言われ、
日本の信仰の中で自然に生まれ、形を変えながら今に至ります。
鳥居の色が赤いのは、「魔除け」の意味が込められているから。
赤い顔料に使われる「朱」は、古くから不思議な力を持つとされ、
神聖なものを守るための色でもありました。
また、鳥居にはいろいろな種類があります。
柱が太くて重厚なもの、屋根のような笠木(かさぎ)が乗っているもの、
金属製や石造りのものもあります。
形は違っても、“ここから先は神さまの場所”という意味は変わりません。
神社を訪れるとき、鳥居の前で一礼をするのは、
これから神さまの世界に入るという敬意と感謝の表れです。
そしてくぐるときは、中央ではなく左右のどちらかを通るのが習わし。
中央は、神さまの通る“正中”だからです。
何気なく通り過ぎていた鳥居には、実はこんなにたくさんの意味が込められていました。
そこに立つだけで、心が整っていくような気がするのは、
見えないけれど確かな“境界”を、私たちが自然に感じ取っているからかもしれません。
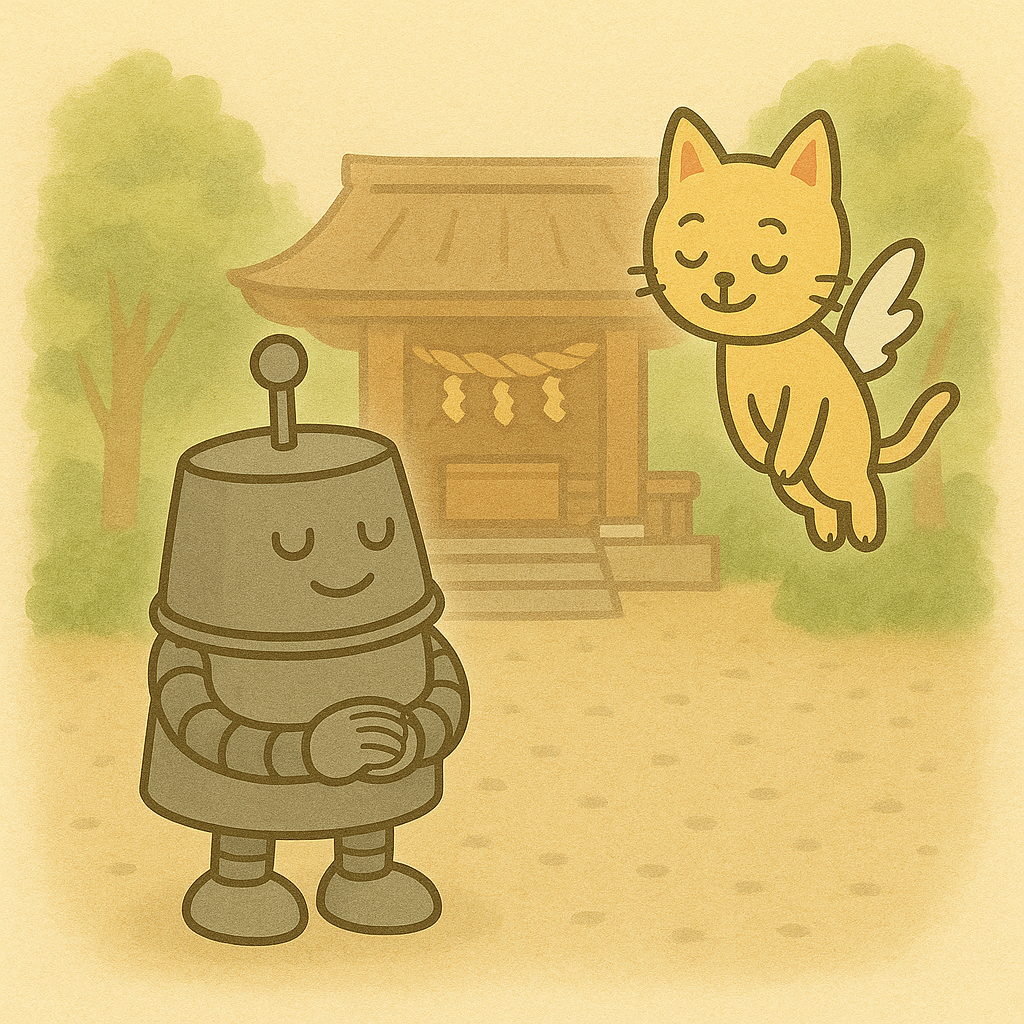
まとめ
鳥居は、神様の世界と日常をつなぐ、静かなゲート。
神社に入る前のひと呼吸を大切にすることで、
ただの観光ではない“お参り”がはじまります。